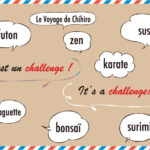毎日の家事のお供に、料理系のポッドキャストを聴くことを楽しみにしています。主に聴いている番組は料理研究家さんと合いの手役の二人が会話形式で、食や料理にまつわるテーマで話を展開したり、リスナーの質問に答えたりするものです。調理法のひとつひとつに理由があることや、料理において自分の頭で考えたり想像したりすることの大切さに気づかされる内容が面白くて聴き入ってしまいます。
例えば野菜の下処理のような行為の背景には、その野菜のアクが強い、表皮が硬いなど食べづらさの要因となる特性が元々はあったのでしょう。その解消法としてあみだされた昔のやり方はもしかすると、クセが弱くなった現代の野菜にはもはや不要かもしれません。皆が言うからとただ倣うのではなく、それを行う目的を知り現状と照らし合わせて判断することで、その行為は単なる「手間」ではなく状況次第で自分で決められる「選択肢」となり得ます。
調理の考え方について興味深い話がありました。日本料理では、例えば旬の頃を迎えた食材をおいしく食べるためには、何かを足していくというより余分なものをそぎ落としていく方向性があるようです。魚であればウロコや皮や骨を取り除いて口当たりのいいお刺身にする。野菜であればゆがいてアクを取り、色鮮やかな見た目とえぐみのない味にする。料理名ありきではなく食材ありきで調理するシンプルさに惹かれます。ところで「ゆがく」を漢字で書くと「湯搔く」となりますが、湯で「掻く」という表現にはなるほど不要なものをそぎ落とすイメージが反映されていると感じました。
西洋料理からは味付けに関する話が印象に残っています。日本食では丼料理やカレーライスのように白米に味の濃いものを合わせて食べることがよくありますが、洋食では基本的にパスタ料理の麺にしても肉料理に添えるマッシュポテトにしても、単体で食べてもおいしいと感じる程度に味を付けておくのだそうです。(白米に合わせるような濃いめではなく)ちょうどよい味付けのソースや肉料理と、ちょうどよい味付けの麺や付け合わせを一緒に食べると、全体としての味もちょうどよくなるという原理です。また複数の食材から一品を作り上げる場合も、各食材に適度に味を付けてから混ぜ合わせると、完成品の味が決まりやすいとのこと。当然といえば当然かもしれませんが、最後までなかなか味が決まらず塩コショウを繰り返すことの多い自分にとっては、目からウロコのお話でした。
さて頭を使って考える話に戻ると、仕事やら何やらただでさえ忙しい日々に台所でまで頭を使いたくない、食事の支度はあれこれ考えずに済ませたい…そう思うのもまた現実です。そんなときネット上にも無数のレシピが存在する現代では、スマホで料理名や食材を検索すればすぐにたくさんのレシピが見つかります。とはいえ手持ちの食材も道具も調味料も、それらのレシピが生まれた環境とまったく同じではない以上、レシピ通りに作ったとしても良い結果になるとは限りません。
しかしここで少し思考を働かせて、「材料を小さく切ったから加熱時間を減らしてみよう」「他の料理とのバランスをとって少しあっさりした味にしよう」のようにアレンジできれば、自分や家族の好みやその時の状況に寄り添った一品になるはずです。そしてそんな応用力を発揮させるために必要なのが、習慣的に「なぜ」「何のために」を考えたり、完成形を想像したりすること。それは何も難しく考える必要はなく、でも思考を働かせるのはある意味トレーニングのようなものだから、やはり日々繰り返すことが大事だと思うのです。
料理脳が活性化して感覚も磨かれていけば、レシピ検索に依存せずにもっと軽やかに料理できるようになるのでは…そんなことを考えながら、ポッドキャストで聞き知ったことを実践しては小さな達成感を積み重ねている今日この頃。台所で過ごす時間が前より少し楽しくなったような気がします。
参考:
最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。
株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に
企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。
翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。
お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。