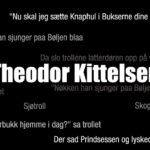日本の美しい四季の中で、その折々の風景があります。皆さんそれぞれの心の中にも、その季節を象徴する景色があるのではないでしょうか。
では、その中で春が来たな、と思うのはどんな景色ですか?私にとって春の訪れを感じさせる景色は、地元新潟の大好きな山の、山肌に現れる「馬」の模様です。毎年、4月から5月初旬にかけて、「跳ね馬」と呼ばれるその馬は、山の中腹に、前足を少し上げた生き生きとした姿を見せてくれます。その少し前の時期から別の山には、「種まき男」と呼ばれる、腰を少し曲げた人のような姿も見えてきます。
真冬には真っ白だった山は、春になると雪が解けて、雪がそのまま白く残っている部分と山肌が現れた黒い部分とで模様をなします。どのような形に見えるかで、人だったり、動物だったり、農具だったり、それぞれの名前を付けて、古くからその土地土地で伝承されているものです。中でも「種まき男(じいさん)」、「種まきうさぎ」など種をまく姿や、農耕に欠かせない「馬」に関するものが多く、古来、暦替わりに農作業のタイミングを教えてきたこれらは、かつては民俗学などでは「雪絵」や「残雪絵」、今は一般的には「雪形」と呼ばれる現象だそうです。信越地方を中心に全国で300以上の種類があるとか。
白馬岳の「代馬(しろうま)=代掻き馬」や、常念岳の「常念坊」、蝶ヶ岳の「蝶」など、山の名前の由来になったとされているものもあります。民話や伝承のもとになったり、その姿からの想像で童話が創作されたりもしています。私の郷土出身の作家である小川未明の『牛女』という童話では、ひとりっきりになってしまう子供を心配しながら亡くなった母親が、春先の山に、牛のような姿の雪形となって現れ子供を見守ります。子供が成長してその土地を離れてしまうと山の「雪形」も現れなくなる、という物語です。
おそらく初めて見る人には、「そういわれてもそんな形には見えないな」と思えるものもあるかもしれません。また、同じ山の同じ「雪形」であっても、集落によっては呼び方も違ったりしたそうです。今は「跳ね馬」として認識されているものが、ずっと以前は「牛」とみなされていたという説があります。小川未明が『牛女』のインスピレーションをもらった山と、私が愛する「跳ね馬」のいる山は同じ山なのかもしれません。呼び方は変われども、昔から、農耕に欠かせない水を育み、季節の移り変わりを教え、人々の暮らしを見守ってくれた豊かな山々への崇敬の想いがそこにあります。
最近の気候の変化や土地の開発でいつかは見ることができなくなってしまうのかもしれません。ずっと変わらないでいてほしいと思う景色のひとつです。
最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。
株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に
企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。
翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。
お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。