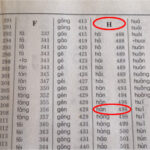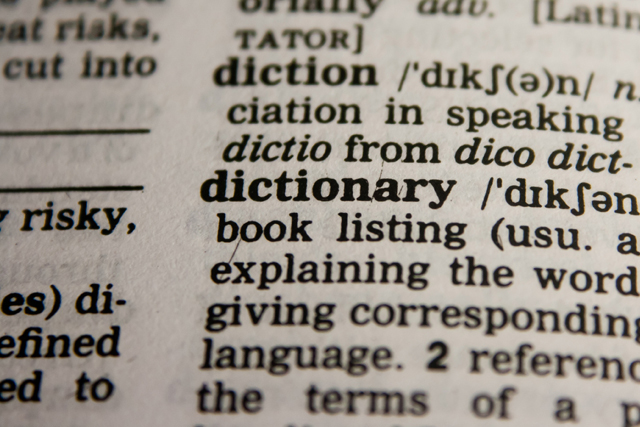
皆さんは普段辞書を使われますでしょうか。
毎日のように辞書を使う方も、学生時代に引いたきりでそれ以降使った記憶がないという方もいらっしゃると思いますが、辞書が世の中に当たり前のように存在するものであることは誰にとっても変わらないと思います。
私自身は、学生時代に語学を専攻し、その後イデア・インスティテュートで翻訳の仕事に携わるようになったため、言葉と切っても切れない関係にある辞書とはそれなりに長い付き合いがあります。外国語学習が好きなため、これまでいくつもの外国語に手を出し、その度に手持ちの辞書の数も増えていきました。学生時代には辞書制作のお仕事にも関わる機会を得て、ほんの少しですが辞書作りの内側を垣間見ることもできました。そのときに感じたことは、辞書制作という仕事に日々尽力されている方々が大勢いらっしゃるという当たり前のことでした。一冊の辞書は多くの人の力を結集し、膨大な作業と時間を費やして作られているものです。だからこそ、普段意識されにくいことかもしれませんが、辞書制作にはドラマがあり、それを題材とした映画があります。私はそういった映画を勝手に「辞書映画」と名付けているのですが、ここでは3本をご紹介したいと思います。
1.『舟を編む』
2013年の日本映画(監督:石井裕也)で、三浦しをんの同名小説が原作です。
出版社に勤務する主人公・馬締光也が辞書編集部に異動となり、『大渡海』という新しい辞書の制作に奮闘する姿が描かれています。
この話はフィクションですが、原作執筆に当たっては岩波書店と小学館の編集部に取材を行ったということで、ディテールの描写が秀逸で、本当にこのような工程を経て辞書が制作されているのだろうと思わせるリアリティを感じます。用例採集、他の辞書の見出し語の確認、見出し語の選定、語釈(見出し語の意味の解説)執筆、循環(言葉Aの語釈にBとあり、Bを引くとAと書いてあるなど)の解決、紙質の確認など、辞書制作ならではの業務が描かれています。
辞書制作の難しさの1つは、物語の前半、「右」をどう説明するか?と聞かれた馬締が、「西を向いた時、北に当たる方が右」と答える場面に表れています。言葉を定義するということは、日本語の運用能力を持つこととは全く異なることだということが良く分かります。
また、辞書は初版完成までに大きなコストが必要(劇中の台詞によれば、「辞書作りはカネを食う」)であることは、ストーリーに大きな影響を与えます。『大渡海』の制作を続けるために、既存の学習辞書の改訂や子供向け百科辞典などの制作を並行し、辞書編集部で売上を上げる必要が生じるところなどは、話に説得力を持たせているように思います。
また、物語の後半、あるミスが発覚する場面があるのですが、分野は異なるものの同じく編集に携わる者として、その緊迫感はひしひしと伝わりました。
一冊の辞書が完成するまでの物語ですが、観終わると思いもかけず、胸に響くものがあります。
2.『博士と狂人』
2019年のアメリカ映画(監督:P・B・シェムラン)で、イギリスのOED(=Oxford English Dictionary)(『オックスフォード英語辞典』)の制作秘話を描いています。原作はサイモン・ウィンチェスターの同名小説で、実話に基づいて作られています。
OEDは1927年初版の、イギリスでは最大、世界でも最大級の辞書ですが、初版完成までなんと70年もの歳月をかけて制作されています。この辞書の特徴は、掲載語数の多さ(現在60万語以上)だけでなく、単語の初出(文献上初めて使われること)例、さらには時代や地域による意味や語形の変化までが用例とともに詳細に記載されていることです。原作小説ではOEDを以下のように説明しています。
OEDは、その編纂の方針において、他の多くの辞典と異なっている。印刷物やその他の記録から英語の「用例」を徹底的に集め、その用例を引いて、英語のあらゆる語彙の意味がどのように使用されているかを示しているのだ。このように大変な労力を要する独特な編纂方法をとった理由は、大胆かつ単純なものだった。つまり、用例を集めて、そこから選び出したものを示すことにより、あらゆる言葉のもつ性質のすべてを非常に正確に説明できると考えられたのだ。引用例によって正確に示すことができるのは、ある語が何世紀ものあいだにどのように使われ、意味のニュアンスや綴り方や発音の微妙な変化がどのようにして生じたかということであり、さらにこれがもっとも重要だと思われるのだが、それぞれの言葉がどのように、そしてもっと正確に言えば、そもそも「いつ」その言語に忍び込んだかも明らかになる。他の編纂方法による辞典では、このようなことはできない。例文を捜しだして示すことによってのみ、その語が過去にどう使われてきたかを余すところなく明らかにできるのだ。
各単語についてこういった詳細な情報を記載するためには、英語で書かれたあらゆる時代の文献を調べ尽くす必要があります。編纂者だけでは当然限界があるため、本を読んで用例を採取し、カードに記載して編集部に送ってくれるたくさんの協力者の力が必要となりますが、OEDを制作するに当たって最大の協力者の一人だったのがアメリカ人医師のウィリアム・マイナーでした。実はマイナーはイギリスで殺人を犯し、精神病院で保護下に置かれていました。ある日マイナーはOED制作のための協力者募集を知り、本を集め、読み、カードを作成し始めます。一方、独学でありながらも多くの言語に通じて広範な知識を持ち、OEDの編集主幹に抜擢されたジェームズ・マレー博士は、用例不足で苦しんでいたところをマイナーの作成した大量のカードのおかげで窮地を切り抜けることができました。マイナーにとってもカードの作成は病状の安定に役立っていて、お互いに必要な関係になっていきます。後に2人は会い、辞書作りを通じて友情を育んでいきます。OEDという実在する辞書の制作背景に重厚なドラマが存在していたことが明らかにされます。
3.『マルモイ ことばあつめ』
2019年の韓国映画(監督:オム・ユナ)で、史実をベースにした物語です。
1940年代、日本統治下の朝鮮半島では、日本語の強制や創氏改名が進む中、朝鮮語学会の学会員は秘密裏に朝鮮語の辞書作りを進めようとしていました。一方、映画館で働くパンスは、仕事をクビになって生活に困り、たまたま学会員の一人の鞄を盗んだことがきっかけとなって、学会で雑務の仕事に関わるようになります。戦争が深刻化するにつれて学会への圧力は次第に強まっていき、警察から辞書作りを妨害されるようになりますが、学会員たちはそれに抵抗し、文字通り命懸けで辞書作りに邁進します。パンスは学会員たちと付き合うことで彼らの持つ言葉への情熱を少しずつ理解するようになります。
全体として重い内容の映画ですが、パンスの性格が人懐こくお調子者であるおかげで映画として観やすくなっているように思います。また、パンスは最初文字が読めないのですが、学会で仕事をしながら徐々にハングルを覚えていき、街の看板が読めるようになり、ついに小説まで読めるようになっていくところは、文字が読めることに対する喜びがあふれていて、観ているこちらまで嬉しくなるような良い場面であると感じました。
この映画で作ろうとしている辞書の特徴は、朝鮮語学会が標準語の制定を最終的な目標としているため、方言まで記載する方針となっていることです。つまり、まず全国の方言語彙を採取して辞書に記載し、その中からどの単語を標準語形として定めるかを考えたいというわけです。しかし、厳しい監視下にある中で各地の方言語彙をどうやって集めるかという問題があり、それがこの映画の鍵になっています。弾圧をくぐりぬけて辞書を完成させることはできるのか、そしてパンスおよび学会員たちがどのような運命をたどることになるのか、スリリングな展開になっています。
以上の三作はどれも、辞書作りの難しさとそれに向き合う人たちの絶え間ない熱意、そして言葉の面白さが描かれていると思います。辞書にはあらゆる言葉が記載されていますが、言葉自体が海のように広大なものであるため(日本初の近代的国語辞典の題名が『言海』だったことが思い出されます)、辞書作りは茫洋とした海を描くような果てしない作業と言えるのかもしれません。また、『舟を編む』でも『博士と狂人』でも描かれていましたが、言葉は日々変化するものなので、辞書には本当の意味での完成というものがありません。このような仕事の上に1冊の辞書が作られていることを知ると、辞書の見方が変わってくるように思います。普段辞書を引かない方も、この機会に一度手に取ってみて、その辞書がどうやって作られたかに思いを馳せてみるのはいかがでしょうか。
参考文献
見坊行徳・稲川智樹『辞典語辞典』、誠文堂新光社、2021年
サイモン・ウィンチェスター、鈴木主税(翻訳)『博士と狂人』、早川書房、2006年
三浦しをん『舟を編む』、光文社文庫、2015年
四方田犬彦「韓国ニューウェイヴ二〇年」『ユリイカ 2020年5月号』所収 、青土社、2020年
最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。
株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に
企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。
翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。
お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。