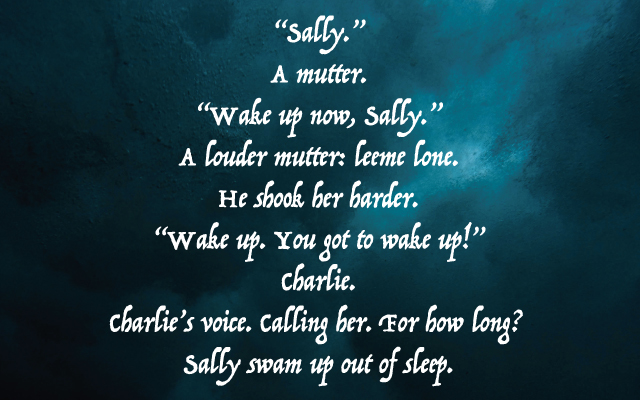
“Sally.”
A mutter.
“Wake up now, Sally.”
A louder mutter: leeme lone.
He shook her harder.
“Wake up. You got to wake up!”
Charlie.
Charlie’s voice. Calling her. For how long?
Sally swam up out of sleep.
この書き出しで始まる長編はスティーブン・キングの『ザ・スタンド』である。
軍の細菌研究所から致死率99.4パーセントのウイルスが漏れ出し、それに気づいた守衛が閉鎖寸前の施設を抜け出して宿舎に戻り、妻を起こすシーンだ。
夢うつつの妻は抵抗して何か言おうとするが言葉にならない(A mutter)。今度は声に出して”Leave me alone”(たぶん)と言ってみるが、眠くて口が回らず、“leeme lone”になってしまう。それでも起こすのをやめない夫に、Charlie.と意識の中で一言呟くが、それだけでたっぷり1行分の時間を費やす。やがて意識は断片的に2ワードから3ワードに増えていって、ようやくサリー(Sally)は目を覚ます。
『ザ・スタンド』は英語版で1100ページ、日本語版で全5巻の長編だ。そんな長編の書き出しは、時代背景や登場人物のバックボーンのような静的なものから始まるほうがバランスがいい。本作が目指したという『指輪物語』(1954~55年)などは前書きでさんざんホビット族の話をしたうえで、本編に入ってもまだホビットの話をしている。じんわりと親近感を与えつつ読者が状況を飲み込むのを待っているようだ。
一方の本作は135mmレンズで切り取ったようなクローズアップシーンから始まる。登場人物の説明は後回しで、親近感など不要と切り捨てている。恐怖は細部とスピードにこそ取り憑く、とばかりに、すぐにトップスピードに乗って恐怖を煽る。
この後、チャーリー(Charlie)とサリーは大慌てで荷物をまとめ、2歳の娘を連れて軍の宿舎を抜け出すことに成功するが、結果的には彼らがウイルスをアメリカ全土に撒き散らすことになる。彼ら自身も次章ですぐに命を落とす。
このエピソードは物語の中では序章にすぎないが、話が進んでもいつまでも通奏低音のように読者の根底に残り続ける。そんなシーンだ。
![]()
April 9 – 10, 2009
Augie Odenkirk had a 1997 Datsun that still ran well in spite of high mileage, but gas was expensive, especially for a man with no job, and City Center was on the far side of town, so he decided to take the last bus of the night. He got off at twenty past eleven with his pack on his back and his rolled-up sleeping bag under one arm. He thought he would be glad of the down-filled bag by three A.M. The night was misty and chill.
『ザ・スタンド』は1978年の作品だが、こちらは36年後の2014年に上梓された『ミスター・メルセデス』。 2009年、リーマンショックの翌年、失業者のオーギー(Augie)は市民センターで開催される就職フェアに前乗りする。車は持っているが節約のためにバスを使い、仮眠のためにシュラフを持って来ていた。市民センターの前には夜中の12時前に着いたが、そこには既に20人あまりの人々が並んでいた。霧が出ていて、寒かった。
オーギーの前には若い娘、ジャニスが赤ちゃんを抱えて並んでいる。ジャニスはシングルマザーで、最近家政婦をリストラされた。赤ちゃんは風邪気味だが、一晩中預かってくれる友人はなくベビーシッターを雇うお金もなかった。夜中の3時頃になると、赤ちゃんが泣き出した。並んでいる人たちから非難の声もあがった。オーギーは自分で使おうと思っていたシュラフをジャニスと赤ちゃんに提供した。ジャニスはシュラフの中でオムツを替え、授乳し、やがて二人とも眠りについた。傍らでオーギーは就職の結果がどうであれ、ジャニスを朝食に誘ってみようと考えていた。
『ザ・スタンド』の書き出しに較べると、穏やかで比較的広い視野で書かれている(レンズで言うと35mmくらいかな)。冒頭に日時を示すことでリーマンショック後の時代背景を明示する。そして次の一文は、女子高生風に言うと「オーギー・オーデンカークは走行距離の割にそこそこ走るダットサンを持ってるけどー」「ガスは高いしー」「仕事もしてないしー」「市民センターは町の反対側だしー」「しようがないのでバスで行くことにしちゃった」とカンマで区切ってリズム良く話し始める。なんとなく楽しい感じさえする。インパクトとしては弱いが、普通に書き出すのがよっぽど嫌だったんだな、という気持ちが伝わってくる。
そして2行目で「Datsun(日産のブランド名)」が出てくる。これはタイトルにもなっている「メルセデス」との対比アイテムなのだろう。文脈的にはメーカー名を出す必要はないが、いきなりDatsunが出て来ると「メルセデスちゃうんかい!」とツッコミを入れたくなる。この辺りも狙ってのことなのだろう。
一方、オーギーとジャニスには就職先が決まって、うまく行けばカップルになってもらいたいところだったが、1章の終わりでメルセデスに乗った犯人に轢き殺されてしまう。なんともひどい話だ。
![]()
‘Wake up, genius.’
Rothstein didn’t want to wake up. The dream was too good. It featured his first wife months before she became his first wife, seventeen and perfect from head to toe. Naked and shimmering. Both of them naked. He was nineteen, with grease under his fingernails, but she hadn’t minded that, at least not then, because his head was full of dreams and that was what she cared about. She believed in the dreams even more than he did, and she was right to believe.
これは『ミスター・メルセデス』に続く『ファインダーズ・キーパーズ』(2015年)の書き出しだ。 『ザ・スタンド』と同じように目覚めのシーンから始まるが、Geniusと呼びかけられたロススティーン(Rothstein)は起きようともせずに、若かった頃の最初の妻の夢を見続けている。
ロススティーンはかつて巨匠と呼ばれた作家で、今は断筆し、人里離れたぽつんと一軒家にひとりで住んでいる。そこにテレ朝のスタッフが、、、ではなく、赤・青・黄のマスクを被った3人組強盗が(なんでわざわざ色違いのマスク買ってんだよ、と総ツッコミ)押し入り、ロススティーンを起こす。一方のロススティーンは強盗なんかそっちのけで、最初の妻ペギー(Peggy)の夢にしがみついている。痺れを切らした強盗はロススティーンをベッドから床に転がり落とす。ようやく目覚めて、自分が置かれている状況が飲み込めて来たロススティーンだが、最大限の賛美をしていた妻の話にオチをつけることも忘れない。
‘but the dream was as gone as Peggy herself, now an old crone living in Paris. On his money.’
実は主犯格の黄色マスク(ベラミー)は、金のために強盗に入ったわけではなかった。ロススティーンの作品に感化されたこの青年は、物語の続きが読みたくて仕方がなかった。断筆したと世間では言われているが、次作の草稿はあるはずだとの思惑で強盗に押し入ったのだ。
この冒頭では「夢」が頻繁に登場する。ロススティーンの実際の夢の中で、若い頃の自分とペギーの夢を語り、そこに物語の続きを読みたいという夢を持ったベラミーが現れて、彼らの夢を壊していくという構造。ペギーの夢はおそらく物語上の装飾だろうが、明暗のコントラストを描く上で効果的に使われている。
前例に漏れず、ロススティーンは1章の終わりにベラミーに撃ち殺される。キングの話にもだいぶ慣れてきたのか、これは予測がついた。
![]()
以前、物語は冒頭の数行で決まる、というようなことをどこかで読んだ気がするが、覚えていない。もしかしたら予備校のテキストだったかもしれないし、「味付けは下拵えの数分で決まる」だったかもしれない。「決まる」って、それはちょっと言い過ぎじゃない?とは思うが、エンディングと同じくらい重要な部分であることは間違いない。
エンディングは物語のクライマックスから精神的な部分へと引き継ぐ重要なパートだが、自由がない。物語は書き終えているのだから、後は修辞的な言葉でまとめ上げるか、クライマックス以上のどんでん返しを持ってくるしかない。
一方のオープニングは自由で、どんな切り口からでも語り始められる。だからこそ、読者の感性に作用するように、ちょうどいい高さのアプローチと、人を惹きつける要素や次の章に続く伏線をどのように盛り込んでいるのか、が大事なのだと思う。
出典:Stephen King: “The Stand” “Mr. Mercedes” “Finders Keepers”
最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。
株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に
企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。
翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。
お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。



